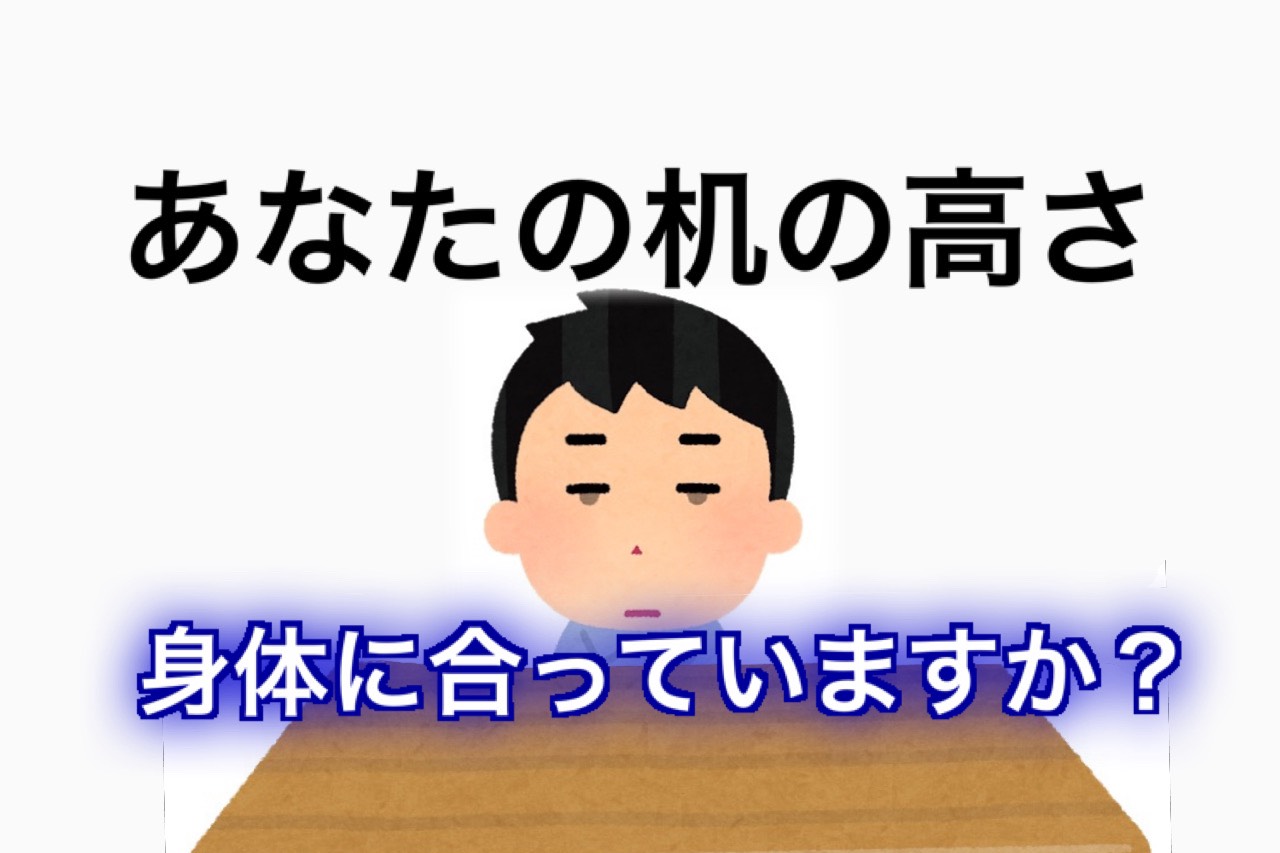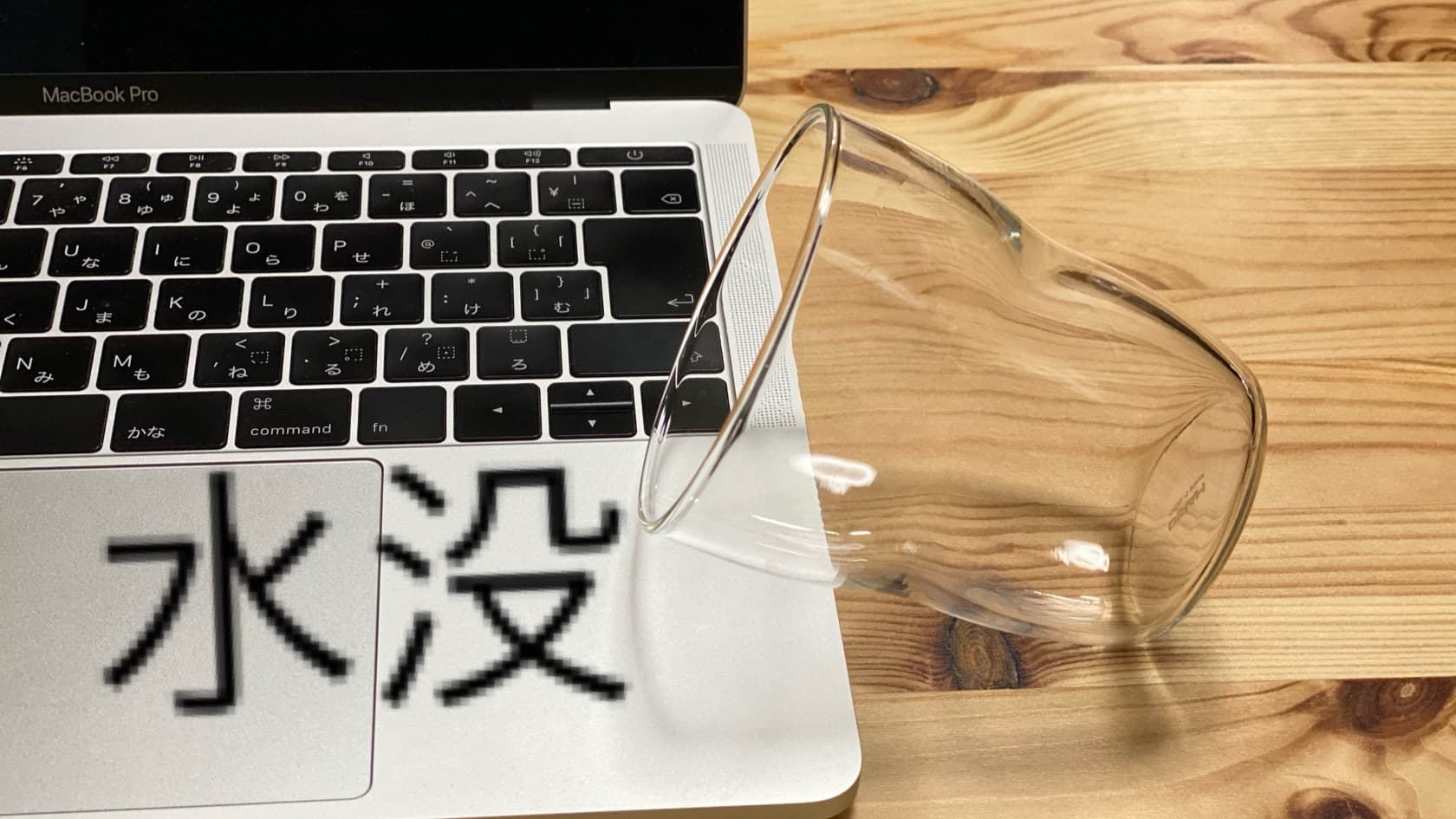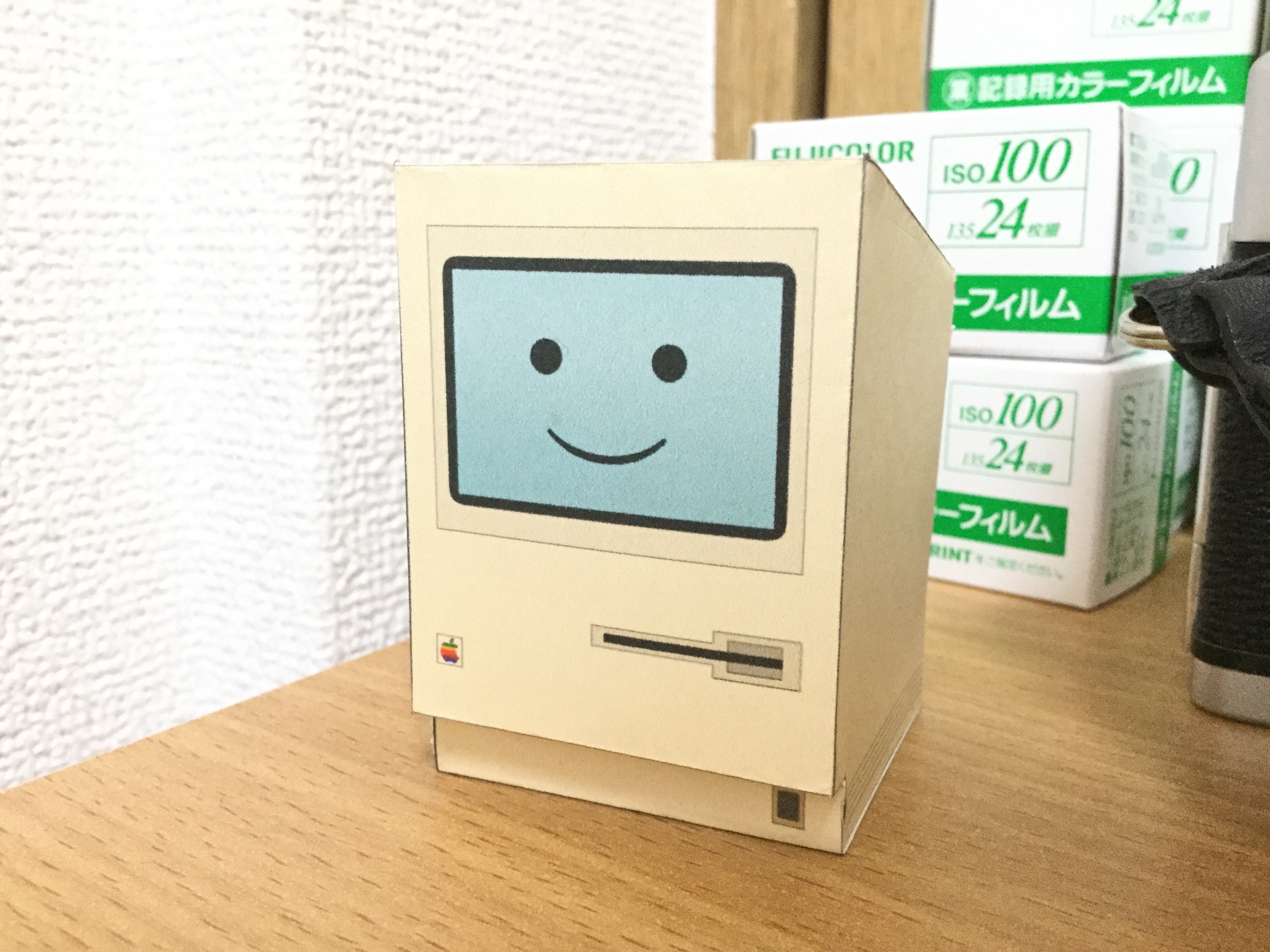こんにちは、ユウジです。
QR/バーコード決済が、かなり普及してきました。
一年前には、一部のコンビニや家電量販店などでしか使えなかったQR/バーコード決済ですが、今では非常に多くの店舗で使用できるようになりました。
今や個人商店でも広く対応してきていて、繁盛している商店街では、殆どの店舗で使用できるようになってきています。
一年でこんなにも急激に拡大するとは思いませんでした。
そんなQR/バーコード決済の普及によって変化した、私たちのスマホ環境について、本記事では解説していきます。
目次
目次
QR/バーコード決済の一年間での浸透具合
2018年12月は、こんな感じでした。(PayPay対応店舗のマップ)

大阪梅田なので、この時点でも多く見えるかもしれませんが、まだ少ないです。
各ビルに一店舗あるかないかという感じです。
この時点では、コンビニはファミリーマートのみ対応していました。
いま同じエリアを出すとこんな感じになります。

大して増えていないように見えますが、これは表示方法が変わったからです。
大阪梅田は増えすぎて、地図として機能しなくなったため(全て表示すると、道路と建物が完全に埋もれてしまう...)、中央周辺の一部分のみクローズアップして表示する方式に変わりました。マップを少し動かすと、表示が変わります。
表示方法が変わらなかったら、ぎっしり埋まっていて面白かったのですが...。
現在では、大手コンビニ全てがPayPayに対応しています。
個人商店でもかなり浸透しました。小規模なタピオカ屋や、たこ焼き屋などでもPayPayに対応した店舗が多く見られます。
QR/バーコード決済は、ほぼ全てのスマホに対応!
QR/バーコード決済は、ほぼ全てのスマホに対応しています。
iPhone 2G(初代iPhone)などの古すぎてアプリに対応できない機種は別です。
ほぼ全てのスマホに対応している理由は、↓
画面があるスマホならOK
だからです。
当たり前すぎて言うまでもないことですが...。
画面がないスマホなんてありませんよね。笑
そもそも、画面がなければスマホとは呼べないと言っても誰も文句は言わないでしょう。
QR/バーコードが表示できればOKです。
あと、QR/バーコード決済アプリのサポート範囲内のOSバージョンであれば大丈夫です。
専用チップが不要 だから全てのスマホに対応できる
QRコード/バーコード決済には、専用チップが必要ありません。
これまでの電子マネーといえば、Suicaや楽天Edyなどのタッチによる決済が主流でした。
Suica、Edyは、それぞれ2001年11月にサービスを開始(Suicaは、最初は乗車券としてのみで、電子マネーとしても使えるようになるのは2004年3月)
タッチによる決済技術は、機能性・利便性・速度において、QR/バーコード決済技術を大きく上回っています。しかし、タッチ決済(Suica, 楽天Edyなど)には、FeliCaというICチップが必要になります。
駅の券売機で買えるSuicaなどの交通系ICや物理カードタイプの楽天Edyなどには、カードの中に非常に薄いICチップが入っています。そのICチップを読取機に近づけた時に、情報が伝達し、決済等ができるようになっています。この時間は非常に短く、0.1秒で完了します。
物理カード内に留まらずFeliCaのICチップは、2004年に携帯電話にも搭載されるようになりました。最初のFeliCa搭載機は、NTTドコモから発売されたパナソニック モバイルコミュニケーションズ製のmova P506iCという機種です。
スマホでは、2010年11月に au(KDDI, 沖縄セルラー)から発売されたシャープ製のIS03という機種で、はじめて搭載されました。
今でこそAndroidユーザーが増えてきましたが、「スマホといえば、iPhone!」というくらい、この頃は殆どのスマホユーザーがiPhoneを選択していたため、スマホでは長らく普及しませんでした。
2016年発売のiPhone7にようやく搭載されると、スマホユーザーにもFeliCaが普及するようになりました。
FeliCaもガラケーと同じく、ほぼ日本でしかシェアのないガラパゴスな状況であり、海外メーカーは見向きもしてくれませんでした。そんななかで、海外メーカーとしては初めてAppleがiPhoneに搭載しました。
ガラケー時代には”おサイフケータイ”として、FeliCa搭載機種が広がりました。
しかし、スマホ時代では日本勢のシェアが低下し、AppleのiPhoneをはじめとする海外メーカーが市場を猛威を振るうようになりました。これが残念なことに、モバイル版FeliCaシェア拡大に穴を開けることになったのです。
iPhone7以降のiPhoneでは、FeliCaを搭載したので問題ありませんが、それ以前のiPhoneを使用しているユーザーも多く、今でも”スマホを当てて決済”というスタイルが不可能な人も結構な割合を占めます。私もiPhone SEユーザー(本記事公開時は SE でしたが、現在は、iPhone 11 Pro です。iPhone 11 Pro に替えた感想は、こちらの記事をご覧ください。) ですので、その一人です。
また、iPhoneを除く海外メーカーのスマホでは、今でも多くがFeliCa非搭載です。
安価で人気な機種として挙げられるHUAWEI P30 Liteなどでは、FeliCa非搭載です。
このように、専用のチップがタッチ決済においては必要です。
画面に表示させるだけのQR/バーコード決済は、これが必要ありません。
日本メーカーのスマホのシェアが日本で高ければ、状況が全く違いましたが、そうは行きませんでした。
いま海外メーカーのスマホが、日本でも市場を席巻しているなかで、FeliCaをモバイルでより普及させるのは厳しい局面です。
スマホでの決済に格差がなくなる
残念ながら、スマホになってからモバイルFeliCaが普及せず、物理カードが必要になるという退化が広く発生しました。
しかし、LINEとSoftBankと傘下のヤフーが、QR/バーコード決済に乗り出したことで、状況は一変しました。
LINEは、LINE Pay
SoftBankとヤフーは、PayPay
という感じで、日本でのQR/バーコード決済の二大巨塔が出来上がりました。
その他にも色々な企業が参入していますが、いずれの企業も二大巨塔には歯が立っていません。
これによって、何が一番すごいのかというと
スマホでの決済の格差を小さくしたことです。
私は、これがQR/バーコード決済の一番の強みだと感じています。
2018年末に、PayPayが100億円還元キャンペーンを実施したことを皮切りに、あらゆるQR/バーコード決済が同様に還元合戦をし、激しいシェア争いが繰り広げられてきました。
また、それと同時並行で、対応店舗を増やすべく、各社が町の個人商店などを1軒ずつ地道に訪ねていきました。
私は、そのようなビジネスを請け負っていた方にお会いしたことがあります。契約成立すると多額の報酬が貰えたそうです。
その方は、昨年末の黎明期から今春にかけて請け負っていたようでした。
飽和を感じて辞めたということで、「普及した今は、全然儲からないよ!」と話されていました。
今やQR/バーコード決済は、コンビニ大手は全て対応し、スーパーや商業施設などでも広まってきました。
QR/バーコード決済が普及する前までは、「スマホを使って決済をするならFeliCa搭載じゃないとなぁ...」と思っていましたが、こういった変化を見て、私は最近「FeliCa非搭載でも良くない?」という風にも思うようになりました。
2018年末からまだ1年経っていません。
それで、これだけ普及したのですから、QR/バーコード決済の普及は凄まじいと感じています。
自販機などを含めると、まだ対応箇所においてFeliCaの方が優位ではありますが、今後の動向次第では分かりませんね。
「ピッ!」の0.1秒で完了するFeliCaは魅力的ですが、「QR/バーコード決済が広まってきたから、FeliCa非搭載のスマホでも良いか!」という判断で機種を選ぶということや、非搭載機を使い続けるという判断も私は悪くないと思います。